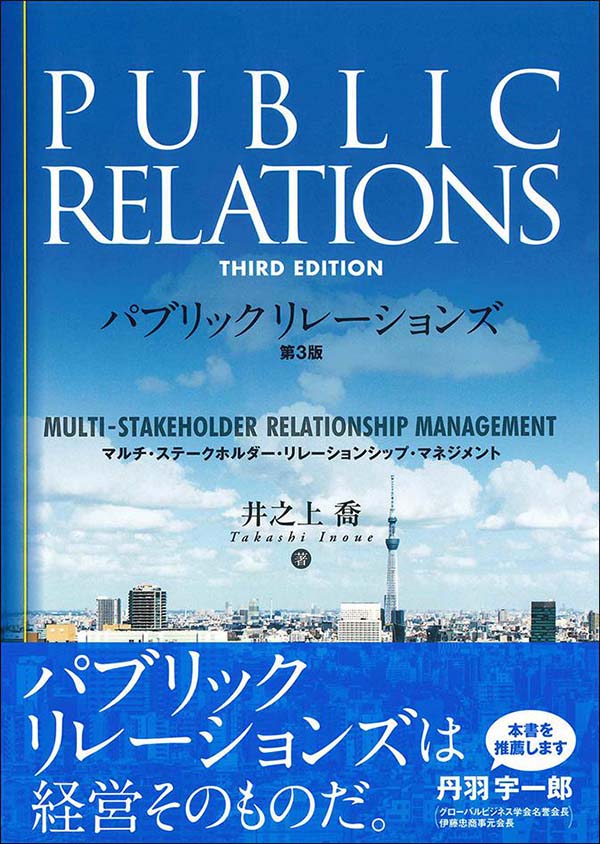トレンド
2021.04.03
スエズ運河の事故が示した危機管理
~そしてパブリック・リレーションズ(PR)の大切さ
皆さんこんにちは井之上喬です。
3月後半、世界の物流や経済に大きな打撃を与える事故が発生しました。アジアとヨーロッパを結ぶ交通の要衝・スエズ運河で超大型コンテナ船が座礁。運河を完全にふさいでしまい、通航ができなくなったのです。この船のオーナーが日本の会社だったため、事の行方を注視していましたが、幸いにも1週間で船の離礁が成功し、通航を再開することができました。世界が注視する中、問題解決に尽力された関係者の方々に敬意を表したいと思います。
長期化懸念も1週間で復旧の朗報
発生から復旧までの経緯を少し振り返ってみましょう。
事故が起きたのは現地時間23日午前7時40分ごろ。スエズ運河内の紅海側に近い地点で、船首が右岸に接触するかたちで乗り上げ、船尾は左岸側へ流れて運河をふさぎ、他の船の航行を遮断してしまいました。座礁した「EVER GIVEN」は全長400メートル、幅59メートル、積載できるコンテナの数は20フィート(約6メートルの短いサイズ)換算で2万個という、現在運航されているコンテナ船の中では最大クラスです。
運航しているのは台湾の海運会社エバーグリーン・マリンですが、船を保有するのは愛媛県今治市に本社がある正栄汽船。国際海運では、船が座礁した場合の回復費用や修繕費用はオーナーつまり船主の負担となるため、責任や補償を含め日本の会社が関与した事故として、連日盛んに報道されました。
事故の原因について、エジプトのスエズ運河庁は砂嵐による視界不良が座礁につながったと見ていると、発生直後の報道が伝えました。複数のタグボートで座礁船を移動させる作業を行ったものの、当日、翌24日も解決に至ることはできませんでした。
25日、正栄汽船は自社ホームページで「現地関係当局および船舶管理会社と協力しながら離礁を試みているものの困難を極めている状況」と発表。運航するエバーグリーン・マリンも日本経済新聞の取材に「いつ運航が正常化し、回復するか見通せない」と回答しました。また、日本政府は加藤勝信官房長官が同日の記者会見で、「現地の大使館などを通じ、情報収集するなど適切な対応を図る」とのコメントを出しました。
そして3日後の26日、正栄汽船は愛媛県今治市内のホテルで記者会見を開きます。
日本海事新聞の報道によると、冒頭で檜垣幸人社長が関係者への謝罪の言葉を述べた後、経緯報告と今後の見通しについて説明。作業は難航しているものの、日本時間で27日夜の離礁を目指す計画を示したうえで、「今は運河の封鎖状態を解くことに注力し、離礁後に船員のヒアリングをはじめ原因究明に動くので、しばらく時間を頂きたい」と話しました。
しかし28日を過ぎても事態は改善しません。エジプトのシシ大統領は、座礁船を軽くするための荷降ろしの準備を指示します。問題の長期化が懸念されましたが、増援されたオランダとイタリアの大型タグボートにより船体が動いたとの情報が入り、スエズ運河庁は29日午後(日本時間同日夜)、ついに「EVER GIVEN」の離礁に成功したと発表しました。
スエズ運河は年間1万8000隻超、1日平均で約50隻の船舶が航行する、欧州と中東・アジアをつなぐ海上交通の大動脈です。ここが通れなければ、アフリカ大陸を南下し、南アフリカの喜望峰を迂回するルートがありますが、変更すると航海日数が1週間から10日伸び、価格や運賃に影響するのはもちろん、船舶の燃料消費も増えるため、地球環境への負荷を増やしてしまうのが懸念の一つでした。
とはいえ、運河内や運河の両端で足止めされた船は30日時点で400隻以上ありました。通過の完了は3日から3日半かかると、スエズ運河庁は見通しを示しました。損害額については、遮断に伴う減収を1日当たり最大1500万ドル(約16億円)と試算、7日間で100億円前後に達すると運河庁はみています。加えて、離礁作業などによる費用も発生し、損害額は10億ドル(約1100億円)を超えると地元メディアに答えるなど、総額は未知の段階です。
これに対し、正栄汽船は4月2日、航海中に発生した損害をその航海に関わる荷主・船社などの関係者で負担し合う「共同海損」という制度の下で、今回の事故補償に対応していく方針を明らかにしました。
パブリック・リレーションズで危機を乗り越える
今回の事故は、企業活動におけるパブリック・リレーションズ(PR)の重要性を確認する事例ともなりました。危機管理の対応はパブリック・リレーションズの基本的な役割と位置付けられていますが、今回のように事業に深刻な影響を与える事象が発生した場合、その後のダメージを最小限に食い止める「クライシス・マネジメント」に加え、並行して行う内外への情報発信やメディア対応の「クライシス・コミュニケーション」が必要になります。
順序や手法を誤れば、企業の存続も脅かす結果となりかねません。そのため、日頃からの情報収集やトレーニングが欠かせません。
今回の当事者である正栄汽船は、社員数29人と人数的には小規模ですが、日本最大の造船メーカー・今治造船のグループ企業です(いずれも非上場)。船舶貸渡業として国内や海外の大手海運会社と日常的にビジネスを展開しており、一般市民的には身近ではないながらも、国際的かつ社会的に大きな役割と影響を持つため、危機管理への意識は高かったのではないかと思われます。
今回は事故発生から3日目に記者会見が開かれましたが、情報収集の準備やメディアへの周知、海外という地理的・時間的制約を勘案しても、地方企業としてはスピーディーな対応だったと思います。また、会見には経営トップの檜垣幸人社長(今治造船社長)以下、専務取締役と常務取締役の計4名の役員が出席。経営陣としての責任や補償に対して向き合っていく覚悟を読み取ることもでき、一問一答を見る限りでは、記者からの質問に丁寧に真摯に応える様子もうかがえました。
断片的なニュースからは、裏でどんな苦労や努力があったかを知ることはできません。しかし、幸いにも船体の損傷や油流出による環境破壊が発生することなく、ひとまず事態の収拾に至ることができたのは、関係者の懸命な努力と連携により思いが通じたことや、日ごろ怠りなく危機管理の準備をしていたからではないかと思うのです。幸運は決して単なる偶然から生まれるものではありません。
ちなみに日本が関係する大型貨物船の事故として記憶に新しいのが、昨年7月から8月にかけてのインド洋モーリシャス沖での座礁、油流出を引き起こした事故です。この時は、事故発生から2週間後に、船舶を保有・管理する長鋪汽船(本社・岡山県)と、運航する商船三井が共同で記者会見を開催しました。今回の事例と比べれば、対応はかなり遅いものでした。
それから約1カ月後、商船三井の池田潤一郎社長(当時)は記者会見で、被害を受けた現地の自然環境回復・地域貢献のために、複数年で総額10億円程度を拠出する計画を明らかにしました。商船三井には法的責任はないものの、社会的な責任を負うのは当然であると、資金拠出に踏み切ったのです。しかしこの時、一部には金で解決したのかとの誤解も見られました。
2つの事例を直接比較することは出来ませんが、事故後の対応が遅れることで、一般社会が受ける印象は大きく異なります。例えその後、法的に求められる以上のことをしても、異なる受け取め方をされる可能性があることには十分留意する必要があります。
私が長年提唱するパブリック・リレーションズ(PR)、つまりステークホルダー(利害関係者)とのリレーションシップマネージメント(関係構築)の視点から考えてみましょう。運河事故では、第一のステークホルダーは海運関係者でした。第二は積み荷の輸送先の生産者・消費者で、幸い1週間で状況は改善されました。一方、油流出など環境問題を伴う場合は、広く長期に環境に影響を与えることから、当初から一般市民も重要なステークホルダーになります。できるだけ早期に、積極的な発信を行うことが不可欠なのはいうまでもありません。
いまやSDGsは企業の成長と存続に不可欠なファクターとなっています。SDGsに取り組む姿勢をいかにステークホルダーに理解してもらうかが、鍵を握ります。そこで必要になる手法が、「倫理観」と「双方向コミュニケーション」、「自己修正」に基づいて、ステークホルダーとのリレーションシップマネージメントを行うパブリック・リレーションズ(PR)なのです。