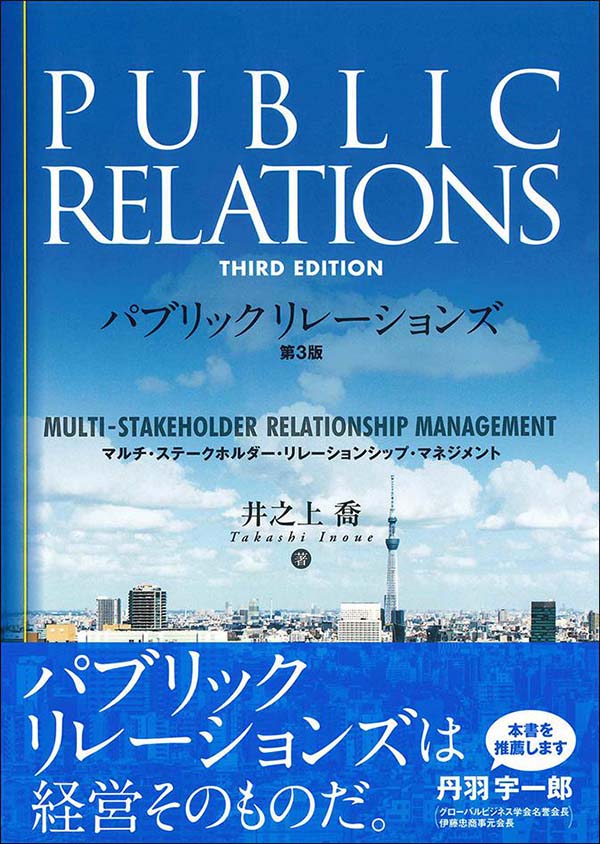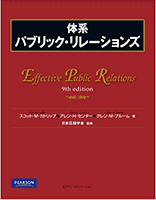トレンド
2025.03.04
ちょっと心配な日本のインフラ
~パブリックリレーションズ(PR)の考え方をベー スにした「危機管理」体制が急務に
皆さんこんにちは井之上喬です。
暦の上では、降る雪が雨へと変わり、農耕を始める時期の目安とされてきた「雨水」が過ぎました。ですが、今年は警報級の寒波が繰り返し日本列島を襲い、北陸など日本海側の地域では記録的な大雪となっています。春の到来が待ち遠しいこの頃ではありますが、2月19日に始まった岩手県大船渡市の山火事は、いったんは鎮火したものの再び勢いづき、いまだ収まっていません。避難を余儀なくされたり、家屋が被害を受けたりするなど、現地の方々には大変深刻な状況であると察します。これ以上災害が広がらないことを祈るばかりです。
急速に進むインフラの老朽化
気になる国内外のニュースは絶えませんが、身近で心配なのが埼玉県八潮市の道路陥没事故です。皆さんもご存じのように、この事故は、1月28日に交差点で道路が突然陥没し、トラック1台が穴に転落して運転席部分は下水道の中を流されてしまいました。原因は下水道管の破損とみられています。
このような事故が起きると、日本のインフラ設備の老朽化は深刻な社会問題であることを実感します。高度経済成長期には、道路や橋梁、上下水道などの多くのインフラ設備が集中的に整備されました。しかし、それらが大規模修繕や更新の時期を迎えても、高額な費用などを理由に十分な維持管理がなされないままになり、今になって安全性の懸念が吹き出ているのです。この問題は、アメリカでも長らく深刻な社会問題となっています。かの国では、第二次大戦以降に新設された施設の耐用年数が限界を迎えているのが実情のようです。
日本、特に地方自治体では財政難から十分な対策が取れず、今回のような事故リスクが限りなく高まっている、それが現状ではないでしょうか。
国土交通省の調査によると、建設後50年以上経過した橋梁は2023年時点で約37%、トンネルは約25%となっており、道路、橋梁、上下水道、港湾施設などが特に深刻な老朽化に直面しています。この割合は今後加速度的に増え、2040年には橋梁で75%にも上り、トンネルも52%となる見込みです。橋梁がある道路種別は72%が市町村道、道路管理者も、市区町村が66%と、地方自治体にかかる責任と負担は一目瞭然です。
これは他人事ではありません。私たちの身近で、橋梁の崩落、道路の陥没、配管の破裂など、様々な事故が発生する可能性が大きくなっています。早急な対策が求められていると言えます。
しかし現状はどうでしょうか。さまざまな災害や事故現場の報道の中で最近よく耳にするのが、「限られた予算と人員の中で十分な対策が出来ていなかった」との言葉です。
なぜでしょうか。インフラは作ったら終わりではなく、機能を維持するために長期的な視点での維持管理計画が必要です。しかし、その重要度が十分に認識されず、適切な手入れをしないままに時が過ぎてしまった。それが今、安全を脅かす「危機管理」の問題となって表に出てきていると考えます。
攻守両面を持つパブリックリレーションズ(PR)が不可欠に
私の専門分野であるパブリックリレーションズ(PR)でも、最近、企業や自治体などから問い合わせが増えているのが、まさにこのような「危機管理」に関するものです。
これはインフラ施設の老朽化に限りません。従来の危機管理の対象となるようなリスク要因には含まれなかった、気候変動などによる大規模災害や、巧妙さを増すサイバー攻撃への備え、そして世界的に注目されている人権問題への対応など、新しくより対応の難しい危機の要因(リスクファクター)への対応が必要になっています。
パブリックリレーションズ(PR)における危機管理の考え方は、「将来発生しうる様々な危機を予め想定し、有効な対策を事前に策定し、必要に応じ対応していくこと」です。その準備と実施には、関係する多くの人びと(マルチステークホルダー)から話を聞き、専門的な判断も加えて、施策に着実に反映することが欠かせません。状況はどんどん変わりますから、常に良好な関係を保って双方向のコミュニケーションを行い、必要な部分は互いに変わり(自己修正)ながら進めることが大切です。将来とは、まだ来ていない時のことですが、その時代が安寧であるように今出来ることを行うこと、そんな倫理観を広く共有することが欠かせません。
これまでの危機管理と言えば、事故や事件、不祥事など比較的限られた場所、時期のものが中心だったでしょう。しかし、今後はインフラ施設老朽化による事故や気候変動による大規模災害など、外部環境の変化による大規模で長期的な新しいリスクマネージメントが必要になっています。
それを実現するのが、攻めと守りの両面の機能を持ったパブリックリレーションズ(PR)です。将来の安全を保つという「守り」に向け、今出来ることを十分に行う「攻め」を両輪で考えること。パブリックリレーションズ(PR)の考え方を基本に、AIなど最新のテクノロジーを大胆に駆使しながら、予算や人員など多くの制約を乗り越える。多様なステークホルダーと共に、地域・組織が一丸となってより実効性のあるリスクマネージメント体制を構築する。そんな備えに、平時から取り組むことが急務だと言えます。