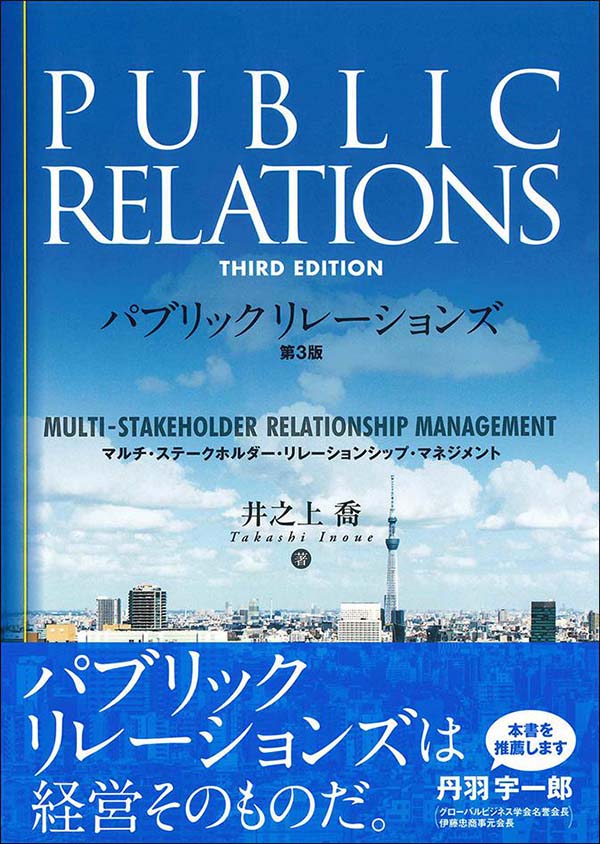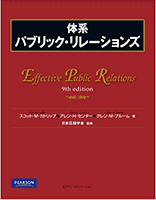トレンド
2025.07.19
井之上パブリックリレーションズは設立55周年を迎えました
〜社員とともに「パブリックリレーションズ(PR)を通し、平和で希望のある社会づくりをめざします
皆さんこんにちは井之上喬です。
関東甲信と北陸、それに東北南部が梅雨明けしたようです。暑さもますます厳しくなりますが、体調管理にはくれぐれもご留意ください。
おかげさまで井之上パブリックリレーションズは、2025年7月4日に設立55周年を迎えました。設立以来、さまざまな面でお世話になった皆さまに改めて御礼を申し上げます。
走馬灯のように駆け巡る
思えば私の仕事人生はあっという間の55年でした。さまざまな事柄が走馬灯のように私の頭を駆け巡ります。
大学を卒業後、入社して3ヶ月半で辞めた日本楽器〔現ヤマハ)の仕事を皮切りに、1970年後半からシリコンバレーのインテルやアップル、MITの人工知能研究所の日本での進出、知名度向上のお手伝いをしました。そして80年から90年代、日米関係が通信、半導体、自動車・自動車部品をめぐる経済摩擦と先鋭化していた時期には、アメリカ側のパブリックリレーションズのコンサルタントを務めるなど、多様なプロジェクトに取り組んできました
80年代は、高度成長を遂げる日本への激しいバッシングが起きた時期ですが、その中で国際PR協会(本部:ロンドン)の理事や本部役員などの仕事も引き受けました。ソビエト連邦崩壊直前のブタペストやモスクワを訪問するなど、激動の世界でパブリックリレーションズの専門家として関わってきました。
これらを通して得た知見や体験をもとに、日本国内でパブリックリレーションズを社会に浸透させようと、教育分野にも活動の枠を広げました。2004年に早稲田大学でパブリックリレーションズの講義を行い、以降、京都大学経営管理大学院、九州大学ビジネススクール、北海道大学などで教鞭を執ってきました。
パブリックリレーションズの理論を体系化するため、2005年には日本パブリックリレーションズ研究所(JPRI)を設立。20年が過ぎ、実践と研究・普及という車の両輪の活動もようやく実を結びつつあります。
パブリックリレーションズをアカデミアに広げ、グローバル人材の育成にも注力する活動は、2012年のグローバルビジネス学会、2021年の日本パブリックリレーションズ学会の発足により進展しています。昨年度は、JPRIで新たに、小中高の教師向けの資格認定プログラムをスタートさせました。
現在は、地方活性化をパブリックリレーションズの観点から実現することを目指した「一般社団法人地方創生パブリックリレーションズ研究所」を新設し、来年度からパブリックリレーションズの科目をオンラインで地方の大学に展開するべく、全国の主要大学に働きかけています。パートナーとして、日本オープンオンライン教育推進協議会〔JMOOC:白井克彦理事長)と連携し、新たなプログラムを準備しています。
大阪万博の年に誕生
井之上パブリックリレーションズが設立された7月4日は、偶然にもアメリカの独立記念日です。55年前に何があったか、少し振り返ってみたいと思います。
大阪で現在開催中の「大阪関西万博」は、開催期間の折り返しを迎えましたが、弊社が設立された1970年は、あの大阪万博が開催された年でした。高度経済成長期の勢いともあいまって、大阪万博は社会現象となりました。当時の日本社会の活力と熱気を表現したような岡本太郎の「太陽の塔」とともに、人々の記憶に残り続けているのではないかと思います。
大阪万博の数々のパビリオンで紹介された当時最先端の科学技術は、来場者の年齢を問わず、衝撃と未来への期待感を与えたことでしょう。企業パビリオンでの展示物には、携帯電話の原型や、動く歩道、今回も話題の人間洗濯機などがあり、日本館では動くリニアモーターカーの模型が注目を集めていたようです。
海外のパビリオンでは、当時冷戦状態にあった米国とソ連の注目度が高かったようです。特に宇宙開発関連は両国とも中心に据え、米国館では「月の石」を一目見ようと長蛇の列が出来ていたのは有名な話です。さらに月着陸船の実物、船外活動用の宇宙服などを紹介していたのも特徴的でした。
現在に戻りましょう。大阪関西万博を訪れた皆さんも多いかと思いますが、55年間の技術進歩には目を見張るものがあります。かつて人々にインパクトを与えたのは機械・生産技術による「もの」に対し、今は生成AIが一気に普及するなど、無限の「こと」が開発され、体験できる時代です。今回の万博は、さらにその先を体験できるインパクトある最先端技術の競演です。加えて、地球環境対策が喫緊の課題になっている現状を踏まえ、「SDGs万博」として各国の自然や文化にフォーカスした展示も人気を集めているようです。
長足の技術進歩を遂げ、ドラえもんや鉄腕アトムの世界がもはや夢物語ではなく現実味を帯びてきた55年の時の流れの中で、改めて井之上パブリックリレーションズの存在価値を考えてみました。
人は進化していますか?
井之上パブリックリレーションズの考えるパブリックリレーションズ(PR)とは、「個人や組織体が最短距離で目標や目的に達するための、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースとしたリレーションズ活動」です。
そしてこの考え方を実践する上で不可欠なのが、「PRライフサイクルモデル」です。PRライフサイクルモデルは、さまざまなパブリック(ターゲット)やステークホルダーとの良好な関係性の構築、維持、発展を実現していく上で欠かせないプロセスの体系で、環をなす継続的な活動であり、あらゆるパブリックリレーションズ(PR)戦略構築の基本となる体系です。詳しくは井之上パブリックリレーションズのホームページをご参照ください。
このパブリックリレーションズに関する基本的な考え方とPRライフサイクルモデルの両輪、つまり理論と実践に一貫して取り組んでいる私たちは、日本のパブリックリレーションズ業界でも特異な存在だと思っています。
現在の世界は、米国の新政権誕生により、これまでの国際秩序が根底から覆されようとしています。政治は混迷し、経済はますます格差が拡大しています。対立と紛争は止むことがありません。技術の進歩には目を見張るものがありますが、我々人間は進歩するどころか退化し、多数の世界レベルの社会課題に直面している気がします。
こうした中、民族や文化、言語、宗教、国境を超えてさまざまなステークホルダーとのリレーションシップ・マネジメントを実践するパブリックリレーションズ(PR)こそ、新しい世界秩序を創る重要な役割を担っていると確信しています。
世界中のさまざまな世代の皆さんが、希望を持てるような未来に向けて、井之上パブリックリレーションズのミッションである「パブリックリレーションズ(PR)を通し、平和で希望のある社会づくりをめざし」、社員とともにこれからも精進してまいりたいと思います。
これまでの55年間、実にさまざまな方々からお力添えで今日に至ることが出来ました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
引き続き大きなご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。