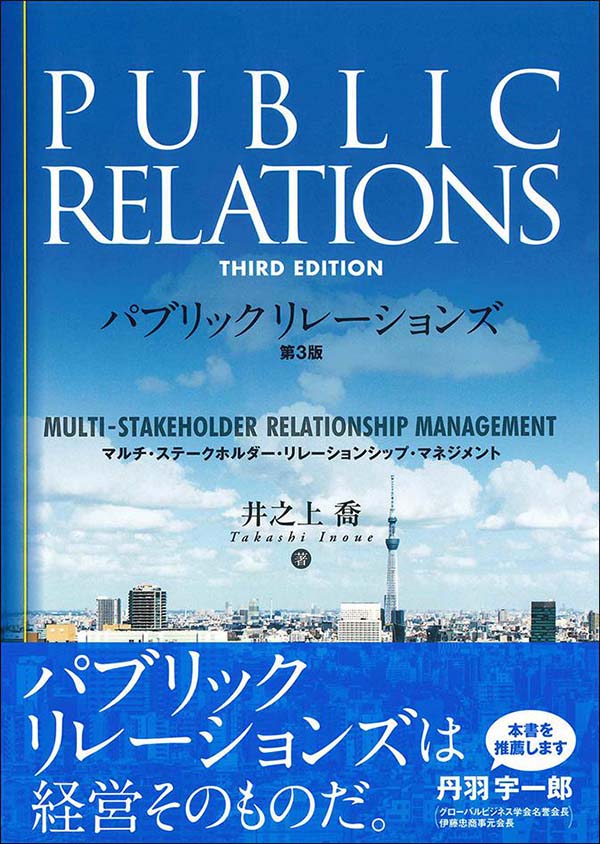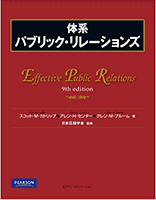トレンド
2025.05.15
「同質性」強い日本型組織の終焉
〜外部環境の変化に柔軟に対応するパブリックリレーションズ(PR)が一つ の解に
皆さん、こんにちは井之上喬です。
ゴールデンウィーク(GW)を皆さんはいかが過ごされたでしょうか。
私はご縁があって大阪・関西万博で講演する機会を頂いたのを機に、忙しい東京を離れ、孫家族と一緒に関西方面を旅行するなど、充実したウィークを過ごすことが出来ました。
人生を豊かに送るためには、メリハリが大切ですね。
改めて考える日本型組織の課題
日本企業に関連する不祥事が絶えません。その一つ、元タレントの中居正広さんと女性とのトラブルに端を発した一連のフジテレビ問題には、依然厳しい視線が注がれたままです。焦点はトラブルをめぐるフジテレビ側の姿勢や対応にあったのですが、最近はフジテレビ側が設置した第三者委員会が中居さんによる性暴力の加害があったと認定し、中居さん側はこれに反論するなど、状況は混沌としています。
この問題を契機に、日本の企業や組織体に関する「組織論」がさまざまなメディアで取り上げられているのは、皆さんもご存じではないでしょうか。
その中で私の印象に残るのは毎日新聞の『「警視庁はフジテレビと同じ」浜田敬子さんが憂える日本型組織の病根』(4月22日、有料記事)です。
浜田さんについてはご存じの方も多いでしょう。朝日新聞、週刊朝日を経てAERA編集長、そしてビジネスインサイダージャパン(BIJ)の立ち上げに関わり、その後独立してフリーのジャーナリスト、一般社団法人デジタル・ジャーナリスト育成機構(D-JEDI) 代表など、さまざまな分野で活躍されています。
興味のある方は是非、インタビュー記事をお読み頂きたいのですが、中の見出しを紹介しましょう。「組織守るが最優先に」「内部告発を受け止めない組織は腐る」「問題社員を出世させる組織は・・・」「取材先と「同質化」する記者たち」「警察官は民間出向を」となっています。
ハイコンテクスト型社会の弱点
この記事が論じるのは、警視庁公安部による冤罪(えんざい)事件「大川原化工機事件」についてです。同社が開発、製造する機器に対し、警察当局は成立しえない法律違反を問い、同社社長など3人を逮捕・拘留。しかし、思い込み優先で事実を軽視した捜査は行き詰まり、検察は公判の直前に控訴を取り下げました。記事はその背景として、同質性の強い、つまりハイコンテクスト型社会である日本型の組織が抱えるさまざまな問題点と、将来に向けての課題や変えるべきポイントを挙げています。
同じ環境や状況、考えを共有し、言葉が少なくても仲間や相手を慮ることができるハイコンテクスト社会は、クローズドな集団では以心伝心や暗黙の了解によって、意思決定や行動が速く効率的など、一定の利点があります。その反面、その集団が倫理観の希薄な環境であった場合、忖度や同調圧力に負けて軌道(自己)修正の声を上げられないなどの危険性もはらんでいます。
つまりハイコンテクスト型の日本社会では、均一性により大きな力を発揮できるプラスの力と、同調圧力に負け組織としての修正が難しくなるマイナスの可能性が裏表に存在しているのです。しっかりとした倫理観が培われていればよいのですが、そうではない場合、さらに上層部が関わるとなると、問題はさらにこじれます。正しい道から外れたまま、組織の暴走を許すことになりかねません。
前述の事件には、これらの問題が顕著に表れています。こうした日本の組織が抱える課題解決に今すぐ取り組まないと、日本社会は世界から取り残されかねません。これまでの失われた30年が、今後も続くのではと、頭を抱えてしまいます。
では典型的な日本型組織とは何でしょうか。これまでの日本企業をちょっとイメージしてみましょう。
まず雇用形態は終身雇用で、同じ釜の飯を食べ、同じ価値観と成功体験を共有する、いわゆる阿吽の呼吸で維持される男性社会――と決めつけるのはちょっと厳しすぎるかも知れませんが、うんうん、と同意される方も多いのではないでしょうか。同質性が非常に高く、内部の事情には敏感でも外部環境の変化には鈍感な男性社会の中で出世した人が経営に関わる、そんな企業が業種を問わず多いのではないか、と考えています。
これが「失われた30年」の根源なのかもしれませんね。
「同質性」の対義語は「多様性」です。これまでの日本型組織を改め、失われた30年を乗り越えてグローバル視点で成長できる、新しい世代による日本型組織の構築は待ったなしだと思うのです。
その課題解決の一つの解が、パブリックリレーションズ(PR)だと思います。
これまで何度も申し上げていますが、私が考えるパブリックリレーションズ(PR)とは、「個人や組織体が最短距離で目標や目的に達する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースとしたさまざまなステークホルダーとの良好な関係構築活動」、つまりマルチステークホルダー・リレーションシップマネージメント活動であると考えています。
この事件では、無理筋の罪を着せられた企業側は、必死に当局側と双方向コミュニケーションを取ろうとし、自己修正を働きかけていました。しかし、当局側は真のステークホルダーを見誤り、自己修正の機会も逸し続けました。何よりも重大なのは、真実を明らかにし社会正義を守るべき立場の組織が、身内の論理を優先して無罪の罪を問い続けるという倫理観の欠如でしょう。パブリックリレーションズ(PR)としてどう評価すべきか、言うまでもありません。
こんな混沌とした時代だからこそ、個人の段階から『倫理観』を備え、勇気を持って『自己修正』機能を働かせられる集団作りが日本型組織に必須だと感じています。
また、このパブリックリレーションズ(PR)の考え方は、経済や政治、文化、あらゆる面で有用です。急速なグローバル化や価値観の急速な変化により、現在の世界は不透明感、混迷が深まっています。性別や文化、民族、言語、宗教、国境など、多くの違いを超えてさまざまなステークホルダーと関係構築を実践する必要が増す中、パブリックリレーションズ(PR)は、持続可能なグローバルビジネスの基盤ともなります。
失われた30年をきちんと検証し、新たな羅針盤のもと、世界の中できらりと光る日本を一緒に作っていきませんか?