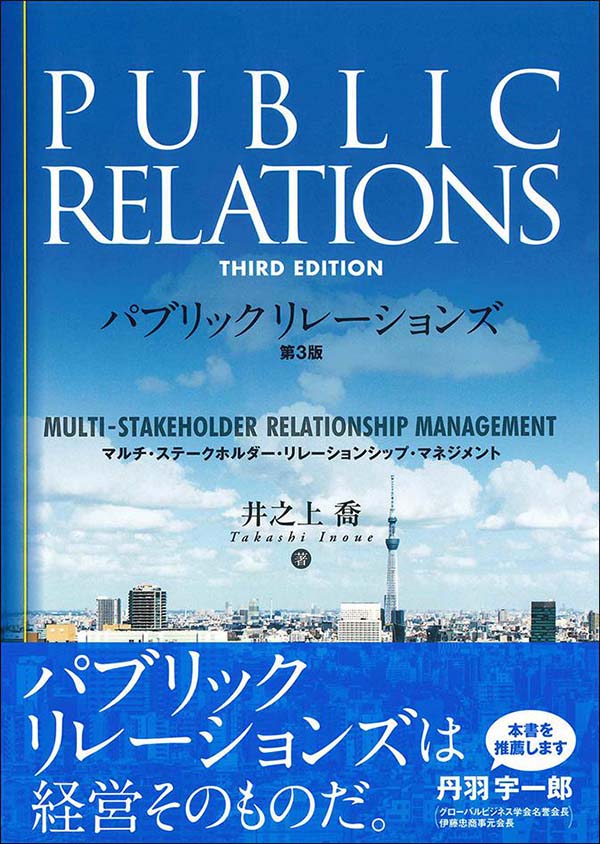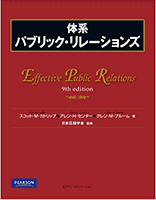トレンド
2025.09.22
世代を超えた社会課題の解決に重要なパブリックリレーションズ(PR)
〜高齢者も若い人たちも生き生きと暮らせる「国家経営」が今こそ必要
皆さんこんにちは井之上喬です。
カレンダーで23日は秋分の日。
長く記録的な暑さの夏から、やっと季節の変わり目を迎えられそうですね。
今年は秋の食卓に上がる秋刀魚も久しぶりの豊漁だそうです。新米とともに大ぶりの秋刀魚で秋を堪能しませんか。
高齢化率、働く高齢者は過去最高に
9月15日は敬老の日でした。
総務省によると、総人口(1億2320万人)に占める65歳以上の高齢者人口(9月15日現在の推計)は3619万人、割合は29.4%と過去最高になりました。これは去年から0.1ポイントの上昇です。
高齢者数そのものは去年と比べ5万人減少していますから、それ以上に出生数の落ち込みによる人口減少が進み、社会の高齢化に拍車がかかっている様子がうかがえます。65歳以上の人口が減るのは、おととし2023年に次いで、比較可能な1950年以降2回目だそうです。高齢者の内訳は男性が1568万人、女性が2051万人で、女性が男性より483万人多くなっています。
そんな中、働く高齢者の数は930万人(2024年)と過去最多を更新しました。総務省の労働力調査によると、前年から16万人増とのことです。
就業率でみると、2024年は25.7%で前年から0.5ポイント上昇。年齢別では、65~69歳が53.6%と過半数が就業し、70~74歳が35.1%、75歳以上が12.0%となっています。
総務省は「人手不足や定年延長などにより、高齢者が活躍する場が増えているので、今後も働く高齢者が増えていくとみられる」としています。
個人差はあると思いますが、元気なお年寄りがこれまでの人生経験や、それに基づく知見を活かし、仕事を通じて社会貢献できる日本を目指したいものです。
日本の子供の幸福度(ウェルビーイング)に課題
高齢化が進む一方で、これからの国を支える日本の子供世代については気になる報告もあります。
ユニセフはOECD(経済協力開発機構)やEU(ヨーロッパ連合)に加盟している国々を対象に、さまざまなデータをもとに子どもの幸福度(ウェルビーイング)についてまとめた報告書「レポートカード19」(RC19)を今年5月、5年ぶりに発表しました。
レポートでは子どもの幸福度を、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの側面から考え、それぞれ2つの指標を使って分析しています。
精神的幸福度はプラスの指標として生活満足度、マイナスの指標に自殺率を用い、身体的健康は子どもの死亡率・肥満率を、スキルについては、学力・社会的スキルの側面から分析しています。
それによると、データが得られた36カ国のうち日本は14位で、38カ国中20位だった前回の幸福度調査(RC16、2020年)よりも順位を6つ上げました。1位は今回もオランダ、2位もデンマークが維持し、3位にはフランスが入りました。
2020年は新型コロナの世界的流行が始まり、その後、学校の閉鎖や運動不足など、数年にわたりさまざまな障害が子供にも降りかかりました。
そんな中、日本は子どもの肥満の割合や死亡率から算出する「身体的健康」は前回と同じく1位で、「スキル」は前回より順位を大きくあげて12位となりました。
しかし「精神的幸福度」は、前回より5つ順位をあげたものの32位と下位に低迷しています。
これは生活にある程度満足している子どもの割合が増えて各国の平均とほぼ同じ水準になった一方、自殺率が上がって4番目に高くなったためだと、気になる分析がなされています。
詳しい内容はレポートをご覧いただきたいと思いますが、以前から指摘されているように、残念ながら、日本の若者は将来への希望を持てていない人の割合が多いことが分かりますね。
厚生労働省の統計でも、2024年の小中高生の自殺者数は529人と、統計が残る1980年以降で過去最高を更新しており、全体の自殺者数が減る中で大変憂慮すべき傾向となっています。
将来に希望を持てない、生きづらさを感じる背景には、少子化や格差拡大による競争の激化、SNSなどネット上でのいじめ、将来の少ない選択肢など、日本が抱える社会課題が垣間見られます。
報告書では、家庭や学校での人間関係などが子どもの心に影響を与えるとも指摘しています。対策として、良好な親子関係を築くための保護者への支援や、学校や地域社会による暴力やいじめなどのリスクへの対処などが欠かせないと各国に呼びかけています。
日本に必要な「国家経営」
少子高齢化が進む日本で、次世代の若者が生き生きと活躍出来る社会をどう作るかとの議論は今に始まった問題ではありません。
私が代表理事・会長を務める日本パブリックリレーションズ学会では、この社会課題に真正面から向き合う「失われた30年検証研究会」を立ち上げ、昨年末に「日本再生へのチャレンジ」として報告書をまとめました。日本が直面する社会課題、グローバル社会の中の日本人の立ち位置はどこなのかを確認するためにこの報告書は国民必携の書だと考えています。中でも大きなポイントは、長期的な視点に立ったサステナブルな「国家経営」が日本に無いとの指摘です。
9月7日、石破総理大臣は、たび重なる党内からの圧力で辞任に追い込まれました。昨年10月1日に就任して1年にも満たない中の出来事です。
憲法7条の首相の解散権を封印し、自らの辞任により政局の安定化を計りたいとの思惑もあるのでしょうが、総理の任期途中の辞任は、国家経営の観点から見れば健全な国政がストップし、機能不全に陥っている状態、と言わざるを得ません。普通の企業であれば倒産です。
戦後約80年で約55人の総理大臣が就任(再任含む)していますが、在任期間は平均で1年5ヵ月に満ちていません。これでは新たな政治の空白を生み政治への不信を高めるばかりです。
自民党は石破総理大臣の後任を選ぶ総裁選挙を9月22日告示、10月4日投開票の日程で行うことを決めました。
国会で少数与党である自民党の総裁が次の首相に就任するとは限りません。しかし、今こそ現行の制度で、与党野党関係なく少子高齢化、経済対策、経済安保など多くの社会課題に国民目線で取り組むことが出来る指導者が求められています。「首相任期4年」を形骸化させている前述の憲法7条を見直し、長期的な国家経営に取り組む環境を実現できる日本の新たなリーダーの登場を切望します。
国家経営の視点で政治を進めるための考え方として私が必須と考えるのは、パブリックリレーションズ(PR)の手法です。
私が提唱するパブリックリレーションズ(PR)とは、「個人や組織体が最短距離で目標や目的に達する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースとしたマルチステークホルダーとのリレーションズ活動」です。
様々なステークホルダーと、それぞれが主張を交わしながらも、柔軟な自己修正を取り入れながら良好な関係を構築し、よりよい社会を速やかに実現する――これこそ政治が目指すべきものである、と思います。
芸術のことを英語でアート(art)といいますが、artとは、経験や知識、研究などにより蓄えた巧みな技の全般を指します。政治家はまさに、パブリックリレーションズ(PR)を駆使し、政治をアートとして巧みに実践、展開する人たちであるべきだと考えます。年代や立場を超えた皆さんとともに、パブリックリレーションズ(PR)を社会に実装する、その先導役になってほしいと強く願っています。