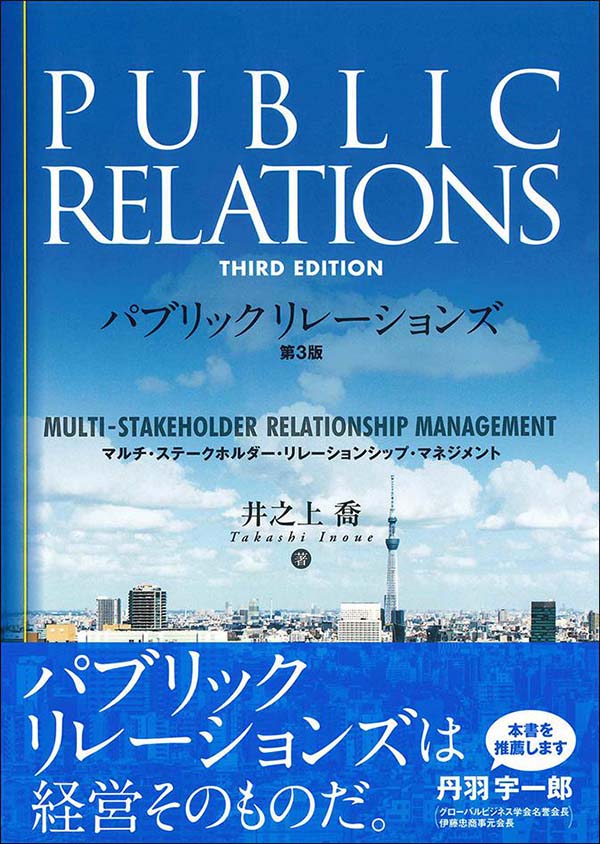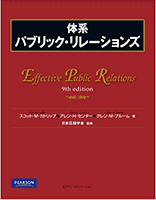トレンド
2025.04.18
歴史学者ハラリ氏の考えはまさにパブリックリレーションズ (PR)の世界!
〜混迷の今の時代に必要なキーワードは「倫理観」、「双方向性」 そして「自己修正機能」
皆さんこんにちは井之上喬です。
4月から新入学、新社会人、会社の異動などで新生活をスタートされた方々も多いと思います。希望をもって新たな一歩を踏み出された皆さんに、幸多かれとお祈りします。
世界の政治や経済の混迷による不透明さの増大、そして温暖化による地球環境の変化など、先の読めない不安定な世の中ですが、明るく、元気を出していきたいものです。困難な時こそ、逆にチャンスの時かも知れません。
4月5日の日本経済新聞に「AIを民主主義の味方に 『知の巨人』歴史学者ハラリ氏」と題した、非常に興味深いインタビュー記事があったのでご紹介します。
ハラリ氏が強調する「自己修正」
ユヴァル・ノア・ハラリ氏はイスラエルの歴史学者です。人類史10万年を情報流通の視点からたどった著書「NEXUS 情報の人類史」の日本語版出版を機に来日しました。さまざまなメディアにも登場したのでご存じの皆さんも多いのではないでしょうか。
現在、人工知能(AI)やSNSが急速に進化、普及しています。それにより、政治や経済、そして私たちを取り巻く日々の情報のあり方も大きな影響を受け、その質が問われるようになっています。このような時代に、民主主義の持続可能性や経済活動の自由はどう変化するのか。そこがインタビューのポイントです。
詳細は記事をご覧いただきたいと思いますが、私が気になった部分をいくつかご紹介します。
まずは米国トランプ大統領の返り咲きに関連してで、「AI革命という、宗教改革や産業革命より重大で途方もない課題に直面している時に、最も影響力のある国に最も危険な指導者が現れた。政治も経済も人と人の信頼関係で成り立つが、トランプ氏もAI革命もそれを損ない、分断を広げる可能性がある」と厳しい見方を示しています。
さらにトランプ政権は「自由な報道や独立した司法など、権力のチェック機能を解体しようとするかに見える。米国は4年に1度、権力を返還し、別の指導者を選択する機会を設ける優れた仕組みと伝統を持つ。私はこの『自己修正メカニズム』が民主主義の根幹だと信じるが、それが危うい」と、自己修正機能が損なわれることへの危惧を述べています。
AIが分断を助長するこの時代、私たちが生き抜くためのカギと考えるのは「自己修正メカニズム」と「信頼の醸成」だ、とも語っています。
民主主義社会に欠かせない「自己修正」
このインタビューの内容は、まさしく私が一貫して取り組んできたパブリックリレーションズ(PR)の考えに非常に似ていると感じました。
指導者が唱える言葉や理念は、人々の間で共有され、具体的な行動へとつながっていかなければなりません。この実践の段階で重要な役割を果たすのが「パブリックリレーションズ」の考えです。
多様な関係者(マルチステークホルダー)の意見を聞きながら対話を進め(双方向コミュニケーション)、必要な部分はお互いに変わりながら(自己修正)、目標実現に向かって最短距離で進んでいくために良好な関係構築活動を進めていく。これが本来の意味でのパブリックリレーションズです。根底には相手の尊重や思いやり(倫理観)が必要であることは言うまでもありません。
パブリックリレーションズは、決して一方的な情報伝達・指揮命令ではありません。自分の立ち位置、相手の立場を考慮しながら、関係者すべてにとって最良の形を目指し、双方向で柔軟に取り組むことが大切なのです。
残念ながら、現在のトランプ政権の進め方を見ると、首をかしげざるを得ない点が多々あります。例えば予算や政府職員の強引な削減や移民の強制送還などで議会や必要な手続きを通さずに事を進めたり、方針に反すると判断した企業や団体、人に対しては訴訟や補助金取り消しで脅したりするなどです。もちろん、政治とは掲げた目標を確実に早く達成することですから、支持者や同党派の人たちには大きな成果だと映るのかもしれませんが。
ハラリ氏は、歴史を学ぶこととは、将来の針路を誤らず選ぶために必須である、と指摘しています。しかし人間は不完全で、間違うこともあります。だから自己修正機能が必須なのです。今回紹介した記事だけでなく、著書「ネクサス」でも自己修正機能について多く触れています。私が取り組んできた「パブリックリレーションズとは、個人や組織体が最短距離で目標や目的に達する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースとしたリレーションズ活動である」、この考えが形を変えて表現されている気がするほどです。
パブリックリレーションズは、今こそ求められているものだと改めて確信するだけでなく、歴史を通じた普遍的な価値があるとの思いを強くしました。皆さんも改めてパブリックリレーションズ(PR)について考えてみませんか?