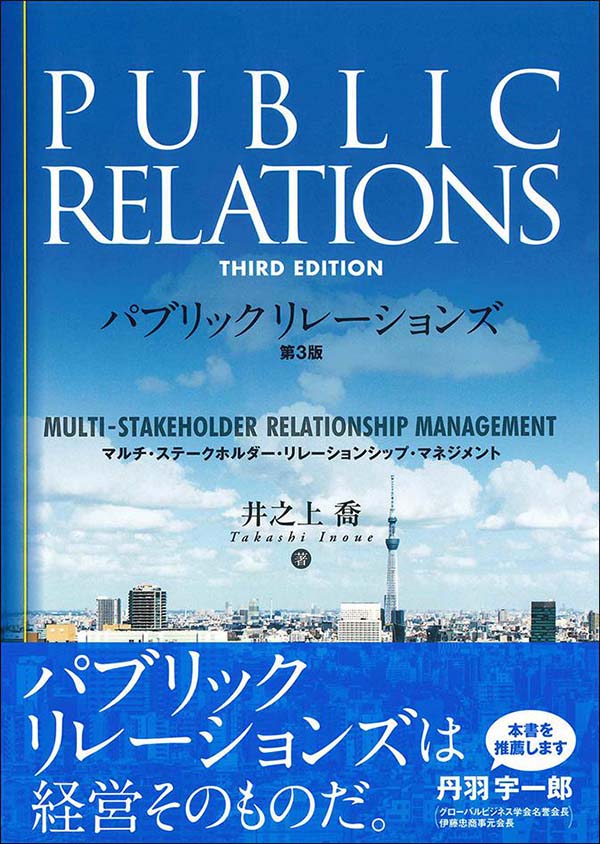交遊録
2013.11.14
「植田正治」生誕100周年の記念写真展〜親子で創り上げた植田正治の世界
皆さんこんにちは井之上 喬です。冷え込みが急に厳しくなりましたが、元気にお過ごしでしょうか。
今回は日本を代表する世界的な写真家、植田正治(1913-2000年)さんのお話です。
植田さんは今年、生誕100周年。100周年を記念する写真展「植田正治のつくりかた」が新装なった東京駅にある、東京ステーションギャラリーで開催されています。
植田さんは、生地(鳥取県境港市)を離れず、山陰地方を生涯の拠点として独特な演出写真で絶大な人気を誇る写真家。日本だけでなく海外においてもその演出写真は「植田調」として知られ、写真誕生の地であるフランスでも日本語表記そのままに「Ueda-cho」として紹介されているほどです。
今回の写真展「植田正治のつくりかた」では、一連のユニークな作品が生まれた背景、手法や作品の変化を通して砂丘の写真家という固定されたイメージを払拭し、親しげな印象の反面で一筋縄ではいかないこの写真家を見直す、といった意図があるようです。会場では、代表作約150作品を展示。開催は来年1月5日まで。
植田正治さんと植田充さん
植田正治さんを語るとき、息子の植田充さんを語らずにはいられません。
私と植田正治さんとの出会いは、植田さんの息子で不世出のアートディレクター、植田充(1940-2003年)さんとの縁によるものでした。父の死後、後を追うように亡くなった息子の充さんと私は、充さんが亡くなる2003年まで、30年に及ぶ親交がありました。
植田充さんは、国内はもとより日・米アートディレクターズクラブ主催による日本グラフィック展(於ニューヨーク)で、それまで日本人が受賞できなかったゴールドメダルやシルバーメダルを数回にわたって受賞した実績のある方でした。
また、彼はファッションデザイナーとして著名な菊地武夫さんのブランド(MEN’S BIGIやTAKEO KIKUCHI)のアートディレクターとして、ファッション界で名を馳せていました。
植田正治さんをファッション写真分野に引きずり込んだのは息子の充さんでした。最初の作品も、充さんがディレクションをとり、鳥取砂丘を巨大なホリゾントに見立てて制作した菊地武夫さんのコレクション・カタログでした。その成果は『TAKEO KIKUCHI AUTUMN AND WINTER COLLECTION83-84』にまとめられ、植田正治さんはADC写真家賞を、充さんはディレクター賞を受賞することになります。
これを契機に、植田正治さんは80年代後半以降、充さんのディレクションでファッションブランドやファッション誌のグラビア撮影に精力的に取り組んでいくことになりますが、写真展ではこうした時期の作品にも会うことができます。
私の会社(井之上パブリックリレーションズ)では、私が日本楽器製造(現ヤマハ)の仕事をしていた駆け出しの頃、さまざまなポスターやパンフレット、そして当時ヤマハが開催し、吉田拓郎、井上陽水、中嶋みゆきなどを輩出した「ポプコン」のシンボル・マークなどのデザインを充さんにお願いしていました。その後の半導体、パーソナルコンピュータなどのハイ・テクノロジー分野のカタログ、パンフレットや広告デザインなども充さんが手掛けたものです。
1984年に世界同時発表されたマッキントッシュのポスターや広告デザインを日本で最初に手掛けたのは、実は植田充さんでした。私の会社には、IBM東京基礎研究所ガイド(IBM宣伝広告賞最優秀賞受賞)やシチズン、シーラスロジックの会社案内など充さんのこだわりの作品が多数残されています。
これは、ある企業の創業10周年を記念した短編映画製作プロジェクトでシナリオ、監督、俳優を公募した際の息子の充さんが制作したポスターです。

植田正治さんの作品の中でも私が特に好きな写真のひとつ、「パパとママとコドモたち」(1949年)を使わせていただきました。
最初にこの写真に接したとき、私の中に戦慄が走りました。それは戦後間もない貧しい時期、粗末な小道具で撮られた写真であるにもかかわらず、時代を超越した、「普遍性とみずみずしさ」を感じたからです。
ちなみに家族全員がモデルとなったこの写真の、右端のお母さんの左隣でピストルを構えているのが、幼少時代の充さん。
植田正治さんの写真を使い、充さんがデザインしたこのポスターは、なんと贅沢なことでしょうか。
相反する二重性の魅力
植田正治さんの写真の魅力について古谷利裕さん(画家、批評家)は、東京新聞(11月1日朝刊7面)の美術評で「植田正治さんは写真というメカニズムそのものに興味を持ち、撮影と同じくらい暗室作業を重視したという。それは、垂直と水平、日常とその切断・再構成とを同じくらい重視したということでもあろう。」
「そして、植田の作品が一方で山陰の風土や自らの家族という身近なモチーフを好み、しかし他方で、砂丘のような抽象的な空間や演出による人工的な操作という自然な文脈の切断を好んだという二重性とも深く関係するだろう。現実の家族に架空の家族を演じさせるという不思議な二重性。この点に植田の写真の魅力がある。」と述べています。
植田正治さんとは息子の充さんを通じて何回かお目にかかる機会がありました。この偉大なるアマチュア写真家は、いつも謙虚で親しみやすく、温かさが感じられました。こうした植田さんの人格そのものが作品に反映され、私にとって作品の魅力にもなっています。
私はこれまで、植田正治さんの写真を展示作品として、写真集のなかで、そして伯耆大山の中腹に開館(1995年)した植田正治写真美術館の収蔵室でも見てきました。誰よりも多く植田さんの作品に接してきたと自負していました。
しかし、今回の150に及ぶ作品の中では、カラー作品など初めて見る写真も多く、これから先も未知の作品を沢山楽しめるのではないかと思い、嬉しくなりました。
「植田調」の演出写真といえば、モノクロかモノトーンをイメージしますが、現在確認されている最も古いカラー作品は1955年以降とされているそうです。
1981年に植田さんは、淡く甘美なソフトフォーカスによるカラー写真集「白い風」を発表しています。その中から3点の写真が展示されていますが、30年以上も前に撮影されたにも関わらず、その映像には新鮮な試みさえ感じることができます。
私の人生に豊かな彩りを加えていただいた植田正治さんと植田充さん。この親子と出会えたことに改めて深く感謝したいと思います。皆さん、お時間があるときにでも是非一度東京ステーションギャラリーへお立ち寄りください。
追記:
植田正治さんの生誕100周年を記念する写真展は、故郷の鳥取県境港市で「植田正治と境港」(11月25日まで)が、植田正治写真美術館では、パリと山陰でそれぞれ同時代に活躍した写真家ロベール・ドアノー(1912-94年)さんと植田正治さんの作品を紹介する企画展が催されています(11月30日まで)。また東京では「植田正治とジャック=アンリ・ラルティーグ 写真であそぶ」が東京都写真美術館で11月23日-2014年1月26日の間、催されます。