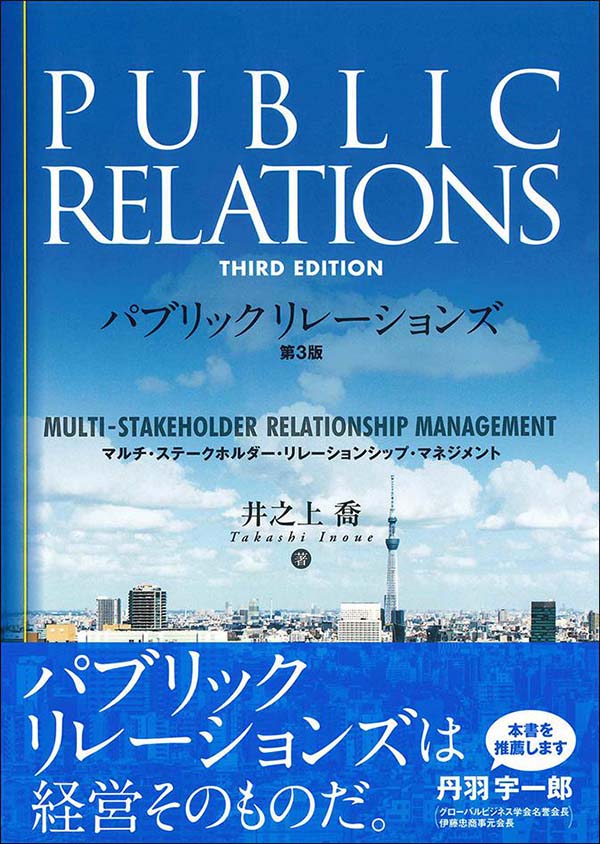パブリック・リレーションズ
2005.07.18
なぜか、いつも本業はパブリック・リレーションズ〜パブリック・リレーションズとともに歩んだ35年間 その2〜
今週は先週の話の続きです。
お恥ずかしい話ですが、私自身この世界に入って、最初の10年ほどはPRという仕事や会社についてうまく説明することができず、いらだたしさを感じたものです。それが解消するようになったのは80年代の初めに、国際PR協会(IPRA:本部・ロンドン)のメンバーになってからです。世界70カ国からの1000名ちかいメンバーは、コンサルタントを始めとする実務家(企業、NGO、政府関連)やアカデミシャンたちで構成されており、IPRAでの活動をとおして、初めてパブリック・リレーションズの間口の広さと、奥行きの深さを知りました。
その頃、日本で使われていたパブリック・リレーションズの日本語訳は「公共関係」とされ、漠然とした意味不明のもので、業界関係者の間ですら解釈の混乱をみていましたが、IPRAでの活動やさまざまな仲間との対話の中で、PRが単なる従来型の広報と認識するのは十分ではなく、より包括的なものであることが解ってきたのです。
特に、パブリック・リレーションズのパブリックの意味が曖昧でよく理解できずにいただけに、「パブリック(一般社会)とは、消費者、投資家、地域住民、政府などさまざまな対象となる因子で構成される」とし、「情報発信者側が情況によってその対象を可変的に設定しターゲットとすることができる」ことを知ったのは大きな喜びでした。
そしてこの手法をリレーションズ活動として体系化したものこそ、20世紀の初頭に米国で登場・発展し早くから学問的にも確立された、パブリック・リレーションズであることだと知りました。
そんな思いで、改めて日本を眺めたとき、日本の社会システムに疑問を抱くようになりました。80年代初頭は、日本の自動車生産が1104万台(1980年)と米国を抜くなど、近代工業国家として世界の頂点に立った頃でしたが、バブルが始まり、国民が酔いしれる日本を尻目に「何かがおかしいと」感じ始めていました。
一方、79年に、ハーバード大学教授のエズラ・ヴォーゲルの著書『ジャパンアズナンバーワン』がベストセラーになり、経済不振の中で、財政赤字と貿易赤字の双子の赤字を抱える米国の対日警戒感が急速に高まるなか、81年にスタートしたレーガン政権下にとっての最優先課題は、いまや最大のライバルで、巨額の対日貿易赤字を抱える日本との関係改善でした。
そんな時期にメンバーとなった(1980年の設立の年)、電気通信分野の、企業、学者・研究者、政府機関の会員で構成されるNGO組織、太平洋電気通信協議会(PTC:本部ホノルル http://www.ptc.org)が毎年一月にホノルルで開催する年次総会では、激化する日米通信摩擦を受けて、政府間交渉の前哨戦ともいえる、非公式会談やロビーイングが繰り広げられていました。
まさに太平洋の真ん中のPTC大会会場が、両国関係者の折衝舞台となっていたわけですが、そこで繰り広げられていた日米両国のやりとりをとおして、アメリカの強力な対日戦略を直接目にする機会を得ました。インテルやアップルなど、カリフォルニア・シリコンバレー企業とは別に、両国の緊迫した政府間交渉を初めて身近にしたのは、82年1月のことでした。
この時期は、いわゆるジャパン・バッシングがよく語られていましたが、アメリカの緻密なPR戦略に比べ日本の正攻法で控えめな折衝術は、パブリック・リレーションズ力において、まるで大人と、子供の差があったといえます。「積極的に、自らの政策や考えをパブリック(国際世論)にアピールするアメリカ」に対し、「自らの考えを明確にせず、パブリックに積極的に訴えない日本」という構図が国際社会に露呈していたのです。
また、第三次中曽根政権下でおきた、87年の東芝ココム事件は日米間に極度の緊張をもたらしましたが、当時、海外から「顔が見えない日本」などと批判されるなか、この事件で経団連は斎藤英四郎会長を団長とするミッションを米国に派遣しましたが、企業トップが本当にPRの重要性を意識し始めたのは、この事件以降だと考えています。このとき同会長は「日本の経済人も積極的に発言すべきだ…」とコメントしていますが、この発言にはがく然としました。つまり、「発言」(情報発信)はコミュニケーションを行なう上で必須かつ最低条件となる行為(しかも一方向の)にすぎず、その上の戦略的な対話や情報のやりとりが重要で、それらは欧米先進諸国がごく当たり前のように取り組んでいることだったからです。
アメリカでは、パブリック・リレーションズを支えている概念が社会に根付いており、大企業もベンチャー企業も、そして政府さえもパブリック・リレーションズの役割や効果を十分認識して日常的な活動・業務を行っているのと比べ、日本との違いは歴然で、経済超大国ともてはやされだした日本への不安感と疑念を払拭することはできませんでした。
80年代後半、日米半導体摩擦の折、アメリカ側のコンサルティングを担当することになり、日本政府のパブリック・リレーションズへの知識も技術も欠落しているために交渉を有利に運べない現実を目の当たりにしました。その後、90年代前半の自動車・自動車部品の規制緩和プログラムに米国企業のために関わり、パブリック・リレーションズ手法をもちいて交渉の決裂をまぬかれた貴重な経験をしました。
そして、90年代に急速に開いた日米間の格差は、パブリック・リレーションズを如何に上手に使いこなしているかが結果として経済力や国力、そして国家のプレゼンスの強弱に表れるのではないか、と確信するに至ったのです。
バブル崩壊後の90年代に入ってからの日本の企業・組織体で頻発する不祥事はあとをたちません。これら不祥事は、企業側が出す情報の流れが、お知らせ的、一方向的な流れで、双方向性になっていないこと、「自己修正」的な概念の欠如していること、「倫理観」があいまいであることなど、パブリック・リレーションズを支えている概念がことごとく欠落していることに起因していると考えています。そのことが日本社会、経済、政治全体に閉塞感をもたらし、行き詰まりを見せているのだと思います。
失われた10年をはるかに過ぎ越した昨今、民主主義社会の下で登場・発展を遂げたパブリック・リレーションズが、いまやっと日本社会でもその必要性が認知されるようになってきました。その要因として、戦後さまざまな規制の保護のもとで驀進してきた日本株式会社も、規制緩和政策の下、経済や社会のグローバル化が進む過程で、何事にも「フェア」で「スピーディ」で「オープン」な対応なくして激しい競争を生き残れない状況になってきたことなども挙げられますが、こうした現状をみるにつけ、日本社会へのパブリック・リレーションズの導入を急がなければならないとの思いを強くしています
しかし残念ながら、社会の要求に応えるだけの人材の供給体制が出来上がっていないことも現実問題として横たわっています。また、教育現場で優秀な人材を輩出しても、欧米のように、PR・広報を専門職として追求し、トップ・マネージメントの一翼を担う、エグゼクティブを目指す人に対する企業の受け入れ態勢の問題もあります。日本社会への導入に向けて、やらなければいけないことが山積しているのです。
35年の軌跡を自分なりに追ってみて、パブリック・リレーションズ以外のさまざまな事業に携わりましたが、どのようなときにも「本業はパブリック・リレーションズにある」という信念にも似た思いから逸れたことは一度もありません。その戦略性次第では、どのような目的をも達成させさせることのできるパブリック・リレーションズにこれからも魅了され続けると思います。そして、日本におけるパブリック・リレーションズの普及に今後も貢献できれば幸いです。