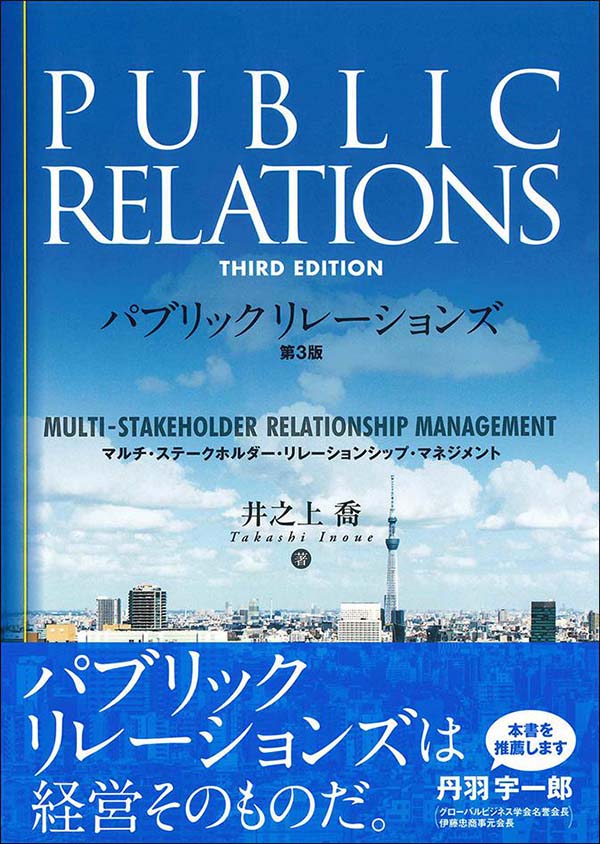パブリック・リレーションズ
2007.10.13
自己のバックグラウンドと向き合う〜より包括的なPRの実現のためにすべきこと
こんにちは、井之上喬です。
皆さん、いかがお過ごしですか。
パブリック・リレーションズが学問として体系化されている米国では、業界で活躍するほとんどの人がパブリック・リレーションズ(コミュニケーションやジャーナリズムの学科を含む)の専門教育を受けてPRの世界に入ってきます。
しかし日本にはPRの専門教育機関がないため、専門的な教育を受けずにこの世界へ入るのが通常のパターン。広報(PR)が専門職として確立されていない日本の組織体では、多くの場合、PR(広報)担当者にはジョブローテーションとして営業や総務部などいろいろな職種を経験した人が就任しているのが実情。一方、PR会社の実務家は、広告を含むマーケティングや新聞記者、雑誌編集などのメディアあるいは一般的な企画や営業職からこの世界に入るケースが多いようです。
自らのポジショニングを知る
どのバックグランドを持つにせよ、これまでの自分の主要な経験を生かすことの重要性は言うまでもありません。しかしその殻に閉じこもってしまうと活動範囲が狭くなります。そこで自分に足りない要素を補う必要性が出てきます。
そのとき肝心なのは、パブリック・リレーションズを体系的に捉え、自らのポジショニングを確認すること。そして自分のバックグラウンドを生かせるのは何処か、そして補強すべき点は何処かを知ることです。
広告やマーケティングのバックグランドを持つ人の場合、スポンサー(クライアント)を優先しすぎる傾向があります。実務家は、クライアントと意見が異なる場合も、専門家として意見を進言すべき立場にあることを肝に銘じ、現場に臨む必要があります。そのためにフィーを頂いているのですから。また、メディア・リレーションズはPRの中核的な競争力です。その活動を成功させるために、メディアと意識レベルを同じにする努力を怠ってはなりません。
逆に、ジャーナリズムのバックグランドを持つ人の場合、メディア・リレーションズに偏ってしまう傾向があります。パブリック・リレーションズにはガバメント・リレーションズやインベスター・リレーションズなど、他に様々なリレーションズ活動があり、それらを統合して取り組む重要性を認識して行動するよう心がけるべきです。
また、ジャーナリズム特有の批判的精神の行き過ぎに気を付けること。批判ばかりでは物事は滞ってしまいます。物事をポジティブに捉え、クライアントとパブリックのWINWIN環境創出がインターメディエーターとしてのPR実務家の役割。バランスを取りながらクライアントや組織に倫理的な行為を促し目標を達成させることが大切なのです。
より大きなステージへ
私の経験を少しお話したいと思います。
大学卒業後に就職したヤマハを退社独立しこの世界に入りましたが、最初の取引先となったヤマハの仕事で、音楽普及のための様々なプロジェクトをプロデュースしたり、新製品開発のための市場調査や製品キャンペーンを行ないました。こうしたマーケティング要素の強い仕事を経験していくなか、ジャーナリズムの要素を強化したいと考え始め、その実現に知恵を絞りました。
そして1973年、メディアへの活動を充実させるため、社内に活字媒体でいう編集機能を持たせ、別会社としてラジオやテレビの制作機能を持つ番組制作会社、「PMC(Pacific Music Corporation)」を設立しました。
活字における最初の仕事は、読売新聞社発行のムック、『オーディオ・カタログ』の編集・制作。この雑誌と書籍を併せた媒体ムックはいまでこそ一般的なメディアになっていますが、当時はまだ先駆け。読売新聞社が、他の新聞社に先んじて発行したこの「ムック」の第二作目、『オーディオ・カタログ』は我々の持ち込み企画としてその編集・制作をまかされたのです。
ちなみに第一作目の「メイド・イン・USAカタログ」(1975年)は、当時、「平凡パンチ」の編集長として名声をあげ、その後「ポパイ」や「ブルータス」など多くの若者雑誌の編集長として出版界を席巻していた鬼才、木滑良久さんによる企画編集。当時の若者が熱狂的に求めたアメリカ文化(特にカルフォルニア)を衣料から住宅に至るまで幅広く紹介し、世のカタログブームに火をつけた歴史的な媒体でした。
そしてオーディオ・ブームに乗った私達の『オーディオ・カタログ』(1976年)は、その第二弾として翌年に発行。また表紙のスーパー・リアリズムのカラフルなイラストはアートポスターとして発売され、さまざまな雑誌に紹介されるなど『オーディオ・カタログ』(写真左)は高い評価を得ることができました。

1978年、同じ読売で三菱電機のビジネス本『ここにナポレオンの辞書がある』(佐藤公偉著:写真右)の企画・編集を手がけました。同書は、進藤貞和社長(当時)のもとで「重電の三菱から家電の三菱」へと変革を急ぐ三菱電機のニュー・イメージを内外に示し、社員の意識改革を促す一助となりました。
一方、電波メディアにおいて先に紹介したPMCは、1979年、FM東京をキーステーションとする全国ネットのラジオ番組「アメリカ音楽地図」を制作。当時の三菱自動車の新製品「ミラージュ」に乗りスタッフがアメリカを横断。現地のFM局やビッグ・アーティストを紹介するという、ラジオ局最大の新しいタイプの番組でした。日本に米国のFMブームを巻き起こし、番組はその後10年以上も続くことになります。
またテレビ番組では、その頃若者の間で人気の高かった、アート映像と音楽を組み合わせた番組、「日立サウンドブレイク」(東京12チャンネル)の海外編を手がけました。取材先も米国、英国にとどまらず、エジプトや、当時政情不安のジャマイカ(日本のTVクルーとしては初めて)など、企画の面白さで取材先を自由に決定し取材クルーを送り込んでいました。
このような媒体制作を通してメディアの視点を自分の中に取り込み、メディアと同じ意識レベルを維持するよう努めたものです。
これらのプロジェクトの成功は、何よりも私に大きな自信を与えてくれました。そしてこの時期に経験したことが土台となり、その後のインテルやアップル社との出会いに繋がったのではないかと思います。
自己のバックグラウンドを生かし、弱い部分を補強する努力を重ねていくことにより、幅広く奥行きの深いパブリック・リレーションズが実現できます。そして高い技術を身につけることで、専門家としてより大きなステージで活躍することも可能となるはずです。
グローバル化が急速に進展する中、企業や国家に求められているのは包括的なパブリック・リレーションズを扱うことのできる専門家です。次世代を担える質の高い専門家が多く出てくることを心から願っています。