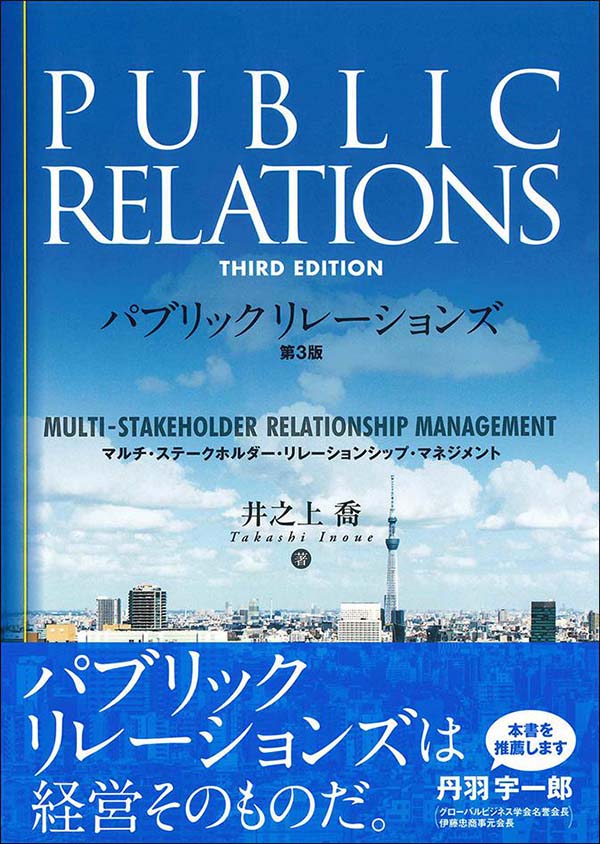パブリック・リレーションズ
2006.11.17
PRパーソンの心得 4 油断
こんにちは、井之上喬です。
11月も半ばを迎え、朝晩の冷えを感じるようになりましたが、皆さん、いかがお過ごしですか。
「油断大敵」とは、よく言ったものです。どんな仕事においてもあてはまることだと思いますが、ちょっとした気の緩みからくる油断が原因で、大きな問題や事件に発展することがあります。皆さんも今までの人生の中で、そういった経験があろうかと思います。今回は、PRパーソンの心得 4として「油断」をお届けします。
30代半ばの時期、私は、現在では世界に名を馳せ巨大企業となっている、当時のシリコン・バレーのベンチャー企業、A社の日本市場進出の際に、コンサルタントとして本社へアドバイスを提供していました。あるときA社は日本の企業B社とパートナー契約を結びました。
私は、かねてからこの提携について疑念を抱いていました。つまりB社はA社にとって、パートナーとして相応しくないのではないかということでした。
現在では、パートナー企業との契約期間など提携の内容はメディアに対してはオープンにするのが通例となっていますが、当時はメディアからの質問であってもケースによっては明確に答えなくとも許された時代でした。
ある昼下がりの突然の電話
A社の日本進出に向けた準備に追われ、私は連日睡眠不足の状態が続いていました。都内のホテルで行われた業務提携の記者発表を含め、さまざまなスケジュールをこなし終えた後、私の疲れはピークに達していました。そんなある日の昼下がり、私はオフィスの自分の部屋の椅子にうずくまるようにして爆睡していました。そのとき私のデスクの直通電話が鳴り響きました。私は半ば反射的に受話器をとりました。突然の電話の主は或る新聞社、C社の駆け出し新聞記者。
その春に 東京大学法学部を卒業したばかりの生真面目で実直な好青年でした。この入社間もないD記者は、ベンチャー企業のA社に興味を持ったようでその頃頻繁に連絡してきていました。
そんな彼から電話が入ったのです。D記者は、「C新聞社のDです。先日の記者発表はありがとうございました」。私は、「こちらこそありがとうございました...」。D記者は、「ところで質問があるのですが、」と話をつづけてきました。私が「あぁ、どうぞ...」と答えると、記者が「先日の記者発表の件ですが、A社とB社との契約関係はX年ですね。そのX年が経ったら、いつでも切れるんですね。そういうことですね」と質問してきたのです。そのときもまだ夢の中にあった私は、「えぇ、そうですね、そういうことですね...」と無意識に返答し、その事実を認める発言をしてしまったのです。
次の日の朝、私はC社の紙面を見て愕然としました。「B社との提携微妙に」と大きな見出しと共に、情報ソースとしてA社のPR会社である、社名と私の名前入りの記事がスクープとして大きく報道されてしまったのです。その記事は、周辺調査から2社の関係が良好に推移していないと主張する内容でした。私のコメントがその主張を裏付ける結果となったのです。
蜂の巣をつついたとはこのようなことをさすのでしょうか、B社からのクレームはしばらく収まりませんでした。この記事がきっかけでA社とB社はしばらくギクシャクしたのです。
電話をかけてきたD記者は以前から、この提携は長くは続かないだろうとの仮説の下に、以前から裏付け調査として周辺取材を行っていたとのことでした。あの時の電話は、彼の意図に合う証言を取るための、いわば確信犯的な取材だったのです。
事実として両社の契約期間X年。終了後は提携解消可能な内容でした。加えて米国本社のトップが、来日時に別のメディアの取材に対して契約内容を詳細にわたり説明していました。その場に同席していた私のなかに、詳細情報の説明に対し外部への発表に問題はないとの安心感があったのかもしれません。
しかし海外から日本市場初参入という極めて重要な局面で、日本の市場に不必要な不安感や混乱を与えないように行動することが、パブリック・リレーションズの実務家として私に与えられた当然の役割でした。それを不用意な対応で台無しにしたのです。私の完全な失態でした。
このような自分自身がコントロールできないな状況の中で、私が取るべき行動は、相手から用件を聞き、折返し電話をするとして一度電話をきり、対応策を決めてから返答することでした。 そして、彼がどのような目的で電話をかけているのかを見極め、感じ取り、少しでも双方にとってこの提携が肯定的なものであることを説明すべきでした。
私は、次の3点で大きな間違いを犯してしまったのです。
一つ目は、日ごろ好意を持つ記者からの電話で気を許していた。
二つ目は、クライアントのトップも他社の取材に対し契約内容を明らかにしていると認識していたので、誰にでも同じように答えても問題はないという安心感を持った。
そして三つめは、深く寝入っていた時の不意の出来事で判断力が決定的に鈍っていた。
これらの3つの理由に加えて、私自身が抱いていた、今回の提携発表についての疑念が心のどこかで響きあい、「えぇ、そうですね、そういうことですね….」と答えてしまったのです。こうして、たった数十秒の会話が、起きてはいけないスクープにまで発展したのです。
常に覚醒した状態でいること
ここから得た教訓は、「パブリック・リレーションズの実務家は常に覚醒していなければならない」ということです。この世界に専門家として身を置き35年以上たった今も、格言にも似たこの言葉を深く心に刻んでいます。
パブリック・リレーションズの実務家や組織内の広報担当者が関わるクライアントや組織を取り巻く状況は刻一刻と変化しています。私たちは、常にその時の状況に見合った最善の対応をリアルタイムで迫られています。 ひとつ一つの対応が、プログラムや問題解決の成否を握っていると肝に銘じておかなければなりません。
幸いこのケースでは、米国内で既に事実が開示されていたことなどから、クライアントからのクレームは一切ありませんでした。しかしこの一件は、プロフェッショナルとしての対応できなかった苦い思い出として、今でも私の中に深く残っています。
スクープ記事を書いた駆け出しの記者は、その後地方へ転出しました。以来、交流が途絶えてしまいました。いま彼はどうしているでしょうか。