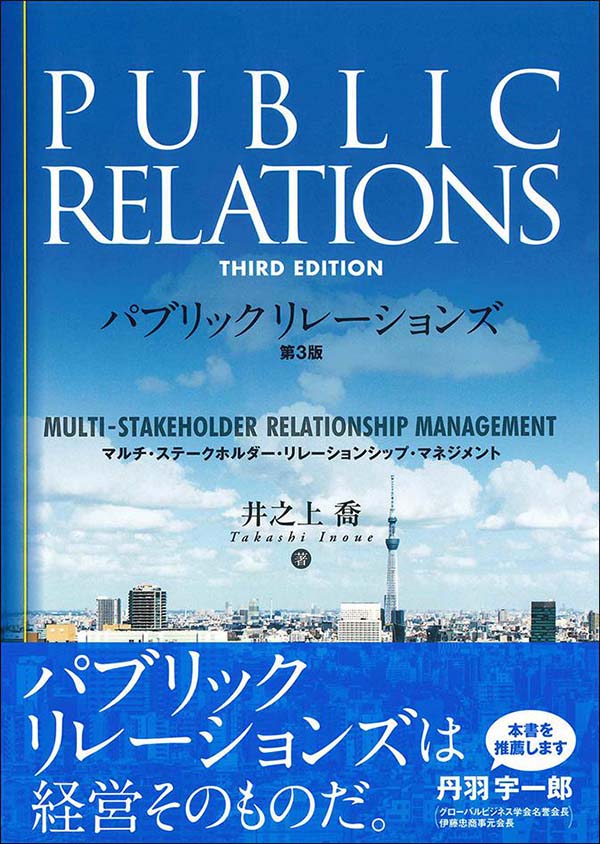時事問題
2010.04.05
反捕鯨団体「シー・シェパード」の違法侵入事件 〜「エコテロリズム」へ毅然とした対応を
こんにちは、井之上喬です。
皆さん東京の桜も満開。「お花見」は楽しまれましたか?
今回のブログでは、シー・シェパードの「第2昭南丸」への違法侵入事件を採りあげます。この事件については新聞やテレビの報道などでご存知の方も多いかと思います。
4月3日付の朝日新聞(朝刊)には、「反捕鯨の元船長起訴」という見出しで、反捕鯨団体「シー・シェパード(SS) 」メンバーでSSの小型高速船元船長ニュージーランド人、ピーター・ベスーン容疑者(44)が2日、艦船侵入などの罪で東京地検に起訴されたことが報道されています。
世界の耳目を集める「劇場型裁判」
シー・シェパードは、環境保護団体を自称しているものの、目的達成を大義名分に捕鯨船やその施設に向けた行動は過激で、これまでもしばしばマスメディアを賑わせています。
1980年にはリスボン(ポルトガル)で捕鯨船を爆破し沈没させ、86年にはレイキャビック(アイスランド)などで捕鯨船と鯨解体工場を破壊。こうしたシー・シェパードの一連の過激行動に対し「米連邦捜査局(FBI)のジェームズ・ジャーボー国内テロ担当部長は02年2月の議会証言で、SSの活動を『エコテロリズム』と表現した。」と朝日新聞(3月13日朝刊)に報じられています。
わが国との関連では、和歌山県太地町でのクジラ魚網の切断事件(2003年11月)をはじめ、第2勇新丸への侵入(2008年1月)、第2昭南丸への小型高速船衝突(2010年1月)、そして2010年には第2昭南丸への薬品ビンの投げ込みや日新丸対するレーザー光線の発射といった妨害行動が起きています。
第2勇新丸への侵入事件で日本政府は、オーストラリア人らSSの活動家2人を拘束したものの、長期化で国際的な批判が高まることを懸念して2日後には洋上で逮捕者をオーストラリア政府に引渡しています。
これに対して当時野党だった民主党が「極めて甘い対応」と批判。SSの暴力行為には反捕鯨国も参加している国際捕鯨委員会(IWC)が全会一致で非難声明を出すなど、NGOからも支持されています。
こうした政治色や国際性の強い事件でもあり、起訴に続く公判では世界の耳目を集めることになります。ベスーン容疑者にとってみれば日本の調査捕鯨の不当性を世界に向けて反捕鯨世論をあおる「劇場型裁判」に持ち込む機会となります。
同様に日本政府にとっても、この事件を見守っている国際社会に対して日本の立場や見解を明確に主張すべき好機となるはずです。
国際ルール破りは許さない
嘉永6年(1853年)の黒船来航は、太平洋で盛んに捕鯨を操業していたアメリカにとって捕鯨船の物資補給(薪、水、食料の補給点)を目的とした寄港地を確保したいという意図があったといわれています。
石油が発見される前、当時のアメリカとイギリスの捕鯨船は、太平洋、大西洋、インド洋、日本近海など世界中でマッコウクジラを獲っていました。この捕鯨は主に鯨油と各種工業素材に利用されていた鯨ひげを採取するといったもので、肉などはほとんど捨てられていました。
日本のようにクジラ全てを無駄なく使用するというものではなかったようです。歴史的に見ても日本は世界一鯨を大切にしてきた民族だといえます。全国各地の捕鯨港付近には、鯨に感謝してその霊を慰める神社が建立されていることを見てもよく分かります。
つまり西欧先進国はかって、クジラを油の原料として殺戮していたのに対して、日本は国民が生きていくのに必要な重要なタンパク源としてクジラを位置づけていたといえます。
どんな問題も文化の衝突に持ち込むと解決は難しくなりがちですが、少なくとも捕鯨に対する根本的な捉え方の違いは、国際社会の中で堂々と主張すべきではないでしょうか?ましてや調査捕鯨が国際ルールとして認められている以上、船の中に侵入したり、乗組員に危害を与えることが許されてよいはずはありません。
その一方で、1982年に国際捕鯨委員会(IWC)の決議で商業捕鯨は禁止されましたが、日本は1987から調査捕鯨として捕鯨を続けています。調査捕鯨をはじめて20年以上経ちますが、この期間にどれだけ調査データを積み上げてきたのでしょうか。反捕鯨国や反捕鯨団体を説得できるだけの科学的なデータは揃えてないのでしょうか。
文化や価値観はそれぞれの国や民族によって異なるだけに、前述したような文化論だけにはまり込めば解決の出口を失いかねません。したがって捕鯨問題は海洋資源の活用と保護の視点からも、科学的根拠を基に論議されるべき問題だと思うのです。
こうした問題にこそリレーションシップ・マネジメント(良好な関係性の維持)機能を有するパブリック・リレーションズ(PR)は不可欠です。それにもかかわらず、この問題についてパブリック・リレーションズ専門家の声が聞こえてこないのは本当に残念なことです。